この記事は、『私とは何か?』からの続きになります。よろしければ、そちらも併せてお読み下さい。
不十分な何か
前回の記事で、『虚無の混沌から、存在を成り立たせる必然が私であると言える』と締め括りました。カッコ良さに全振りしたような表現ですが、間違ってはいないと思います。
それでは、そこで、ある疑問が生まれます。その『私』の存在を、何が保証するのか?ということです。言い方を変えるなら、何が私を存在させているのか?とも言えるかと思います。前の記事でインド哲学などによれば、『認識するもの』と『認識されるもの』が対になることで存在は完成すると言われています。認識するもの、ないしは認識されるもの単体では存在しているとは言えないとも書きました。
つまり、存在するものは、その存在を何者かによって認識されることにより、存在していることを完成させる、あるいは実存させるのです。ちなみに、ここで使っている『実存』とは、実存主義なとで使われる実存とは違います。実際に存在しているという意味です。で、実際に存在していると言っても、多くの人がそんなの当たり前だろうと仰るかも知れません。しかし、先に述べたインド哲学などを例に引くまでもなく、それだけでは存在している事実を証明するには不十分なのです。
間接作業である認識の限界
そもそも永遠に存在できるものはありません。永遠に存在できるなら、実在する事実を求めることもないのです。そのようなことをしなくとも、存在は永遠を保証されているのですから……。
しかし、あらゆる存在がいつか消滅してしまい、存在を前提とした消滅したという事実すらが消滅してしまうことになるのです。そして、わずかな拠り所である、存在しているという事実すら、認識されたものにしか過ぎません。僕たちは、直接存在する事実を体験しているのではなく、認識された存在の虚像を認識しているのです。
これは、映画・マトリックスの世界で、主人公のネオが置かれていたシュチュエーションと同じです。マトリックスの元ネタですが、『水槽の中の脳』という思考実験もあり、当然同じ問題を提起しています。水槽の中の液体に脳が浮かべられ、その脳はコンピューターに繋げられ、仮想現実を見せられています。
あなたが現実に存在すると思っている世界は、実のところこのような脳が見ている幻覚ではなかろうかという問い掛けです。そして、この問い掛けがもたらす可能性を、断定的に否定することはできません。デカルトが示した『我思う故に我あり』という発見でさえ、コンピューターが見せている幻なのかも知れないのです。つまり、あなたはあなたという存在に確証を持つことはできないのです。
そうなのです。僕たちが、存在することに対して、本当に確証を持ちたいのは『私』なのです。『私』が認識することによって、『認識するもの』と『認識されるもの』を対にすることができたとしても、存在を本当に証明したいのは『鍵を掛けた引き出しに仕舞われた一冊の本』ではないのです。それは、不確定な曖昧さの中に漂う、あなたという切実な『私』なのです。
『私』は『私』を認識する
認識する主体が『私』だとして、『私』を実在させるためには、何を客体として認識しなければならないのでしょうか。引き出しの中の本は認識されることによって存在することができたのです。そうだとすれば、『私』の存在を実在させるために、『私』に認識されるべきは『私』ということになります。えっ? 私ばかりですけど……と訝られるかと思います。そうなのです、『私』ばかりだからこそそれは価値を持つ言えます。前の記事で、青年に対して、お釈迦さまは『アートマンを探せ』と仰っていたことを紹介しました。そこでアートマンを探すのは『私』で、探されるのは本当の『私』であるアートマンです。やはり、『私』が『私』を探すのです。
そこで問題になるのは『私』は『認識する私』と『認識される私』という相反する状態を、同時に満たせるのかということです。それは、『認識するもの=主体』と『認識されるもの=客体』という正反対の性質を持っているのです。これは大きな矛盾に思えます。そして、もちろんその通りなのです。通常、それは一つの存在の中に共存するものではありません。自分と他者が一つになる境地ともいえます。それが実現してしまうのなら、すべてが自分になってしまう境地なのです。そして、その境地が『悟り』であると言えるだろうと思います。
密教において、悟りは、即身成仏といって自我と真我が一つになった状態を言います。心理学者のユングの興した分析心理学でも、自我とセルフ(自己)が自我セルフ軸が崩壊することによって一体になった状態を悟りと定義しています。
このことに関して『悟りとは何か?』という記事で詳しく書いています。ただ、考えが纏まらず、若干支離滅裂な部分があるので、もう一度書き直すか、新しい記事を書くつもりです。
私という唯一のもの
ただ、主体としての私による、客体としての私への合一が可能であるなら、それは単に自己の存在証明に留まらず、真理への到達とすら言えるのかも知れません。何故なら、私という一つの存在に、『見るもの』と『見られるもの』という二つの条件を共存させているからです。つまり、何ものにも依らず、それのみによって存在を完結できるということです。
『私とは何か?』の中で、『私』とは、本来一つのものから、認識する機能が必要とされ、認識する必然として主体が生まれ、それは『私』と呼ばれたと書きました。これは時間的順序ではなく論理的順序なのですが、認識する主体も認識される客体も元々一つだったのです。そして、本来は今も不可分な一つです。そうであるなら、その片方が『私』と名付けられた以上、それは一つのものなのですから、もう一つも『私』と呼ばれることになるのです。
さらに言うなら、認識するものが認識されるものなのですから、唯識がもたらす『認識される一切が幻に過ぎない』という事実にも影響されることはありません。認識される客体が、同時に認識主体でもあるからです。そして、その条件を満たすのは、認識主体である『私』だけなのです。それは、『私』だけが、認識するという幻の内側で認識することができるからです。それが可能なのは、唯一『私』だけだといえます。つまり、私を実在させることができるのは、『私』だけなのです。
そして、『私』は個人を指すものではないともいえます。それは認識するということの表現の違いです。認識するためには、主体ということが必要とされ私が生じた。そして、個という概念が生まれた。つまり、個という感覚は、本質ではなく、後付けなのです。そうだとすれば、無数の私が、一つの『私』の現れに過ぎないのかも知れません。

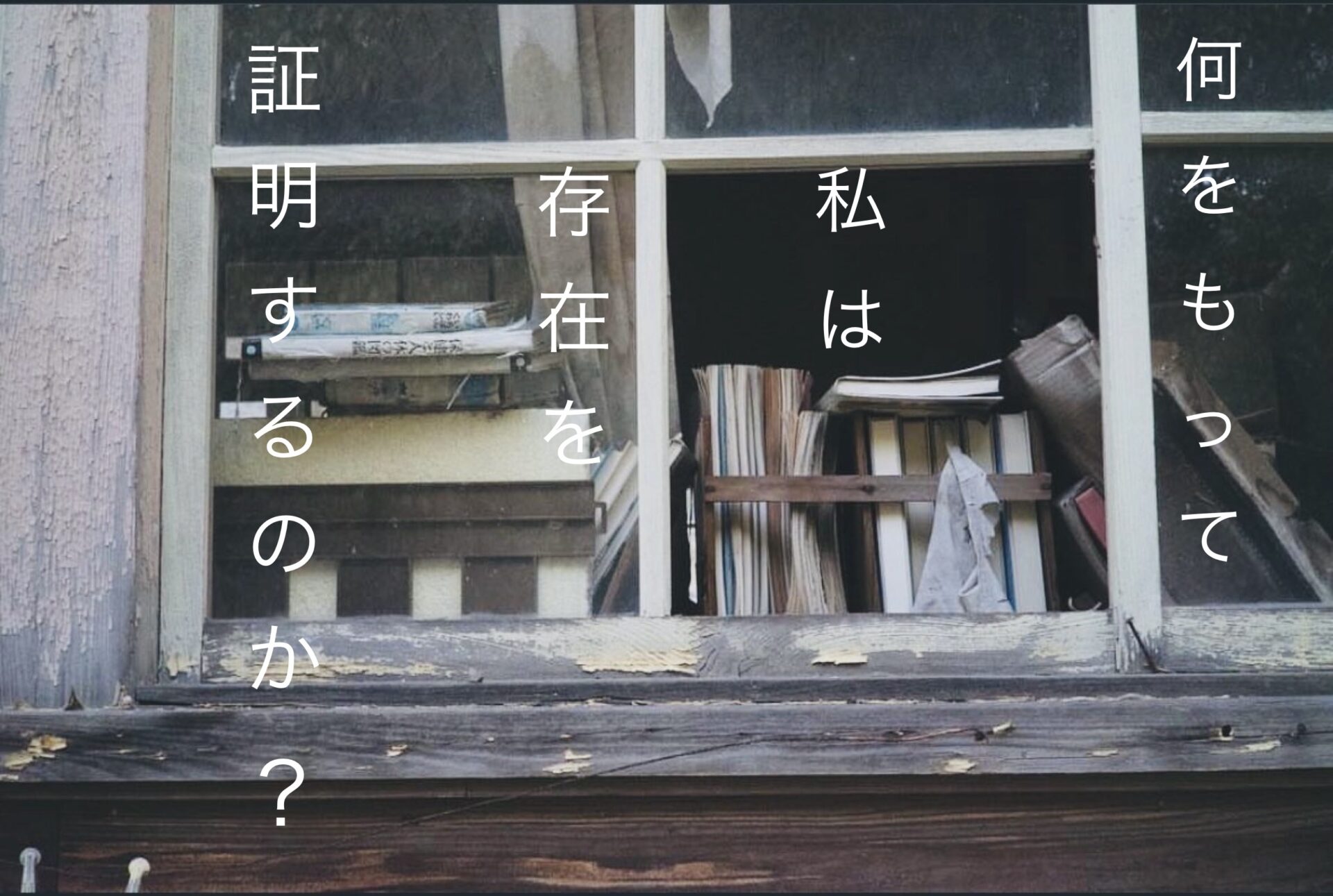


コメント