以前、高野山の信仰には、一神教的側面があると書きました。今回は、その一神教的要素である弥勒信仰に関して観ていきたいと思います。
弥勒信仰と浄土
高野山真言宗の救済といえば、即身成仏です。大乗仏教では、悟りを開き仏になるためには三劫という期間修行して初めて成仏することができるとする三劫成仏(さんごうじょうぶつ)という考えがありました。劫というのは仏教が説く最長の時間単位で、一劫は一辺四十里四方の石を、天人の羽衣で百年に一度払い、その大きな石が擦り減って無くなってなお終わらない時間の長さです。そして、その三倍の時間が三劫となります。
誰しも『そんなにも待てない』と思うのですが、そこで現れた考え方が即身成仏です。即身成仏とは、今、この身のまま仏になれるという教えです。三劫成仏と比べれば、びっくりするほどお手軽です。しかし、それにしても、三劫成仏と比べればお手軽というだけで、出家して厳しい修行をしなければならないし、密教は秘密の教えだからなかなか一般人に学べるものではありません。
そこで必要とされるのが、弥勒信仰になります。弥勒信仰とは、インドで生まれ、六世紀頃の奈良時代には既に日本でも信仰され始めていた仏教の教義です。教えとしては、お釈迦さま入滅後56億7千万年後の未来に、弥勒如来が現れ人々を救うというものです。何故今すぐ救ってくれないのかというと、弥勒如来はまだ悟りを開いていなくて、弥勒菩薩として兜率天(とそつてん)という浄土で悟りを開くため修行中だからということなのです。ただ、弥勒菩薩が悟りを開き仏になることは保証されており、それが56億7000万年後なのだそうです。
諸説あるとは思うのですが、弥勒信仰は、地中海世界に広まっていたミトラ教と起源を共にしているようです。もともと、インド、イラン辺りで信仰されていた宗教が周辺地域に広がったのでしょう。高野山に弥勒菩薩を想うと、古代ローマで信仰されたミトラ神の残響を聴くかのようです。ちなみに、ミトナ神は太陽神。弥勒菩薩は大日如来の化身で、大日如来は太陽を象徴する仏。日本の最高神はアマテラスで、もちろん太陽神。まあ、相性が良いのでしょうね。

このまま弥勒菩薩を待っていれば良いのかと思いきや、平安時代になると阿弥陀信仰が日本各地で盛んになってきます。弥勒信仰は待っているだけでは駄目で、それなりに瞑想などをしなければならなかったのですが、阿弥陀信仰になるとただひたすら念仏を唱えていれば、悪人ですら浄土に行けるということになります。弥勒信仰よりも阿弥陀信仰の方がお手軽なのです。56億7000万年も待たなくても良いですし、悪いことをしてても念仏さえ唱えていれば問題ないのです。この辺は後出しジャンケンみたいなものだと感じます。きっと後発の方が、それまでの教義を前提にして、より魅力的な教義を作れる分、有利なのだと思います。
ともかく、弥勒信仰と阿弥陀信仰は良く似ており、両者が将来浄土に行き救済されることを約束します。それは、多神教である仏教においては、非常に一神教的な教えに見えます。キリスト教とかの、救世主がやって来て、神の国に復活するってやつですね。即身成仏や禅がプラクティスの宗教だとすれば、浄土信仰はストーリーの宗教だと思えます。それは、自力と他力という信念に対する態度の違いとも言えるでしょう。
弥勒菩薩の降臨とブルーシート
そして、弥勒菩薩が弥勒如来になった暁には、この地上に降臨し、三箇所で人々を救うために説法をすると言われています。その三箇所の内の一箇所が、高野山は奥之院だというのです。さらに、高野山では弘法大師・空海が同時に現れ、衆生には理解不能な弥勒如来の言葉を分かりやすく翻訳してくれるというのです。弘法大師が今も奥之院に入定されているのは、この時のためとも言われます。ちなみに、弥勒菩薩と弥勒如来という言葉を使い分けていますが、菩薩は悟りを開くために修行中の呼び方。如来は悟りを開らき、仏になった後の呼び方です。

とはあれ、弥勒信仰において、56億7000万年後に行われる弥勒如来の説法はすべてが結実する圧倒的クライマックスなのであります。そして、弥勒信仰を持つものであれば、必ずその瞬間に立ち会いたいと願う訳です。ただ、当然その時には現世の自分は死んでおり、例え輪廻していたとしても、高野山の奥之院に居合わせられるか分かりません。場所は高野山の奥之院、時間は56億7000万年後と決まっているのになんとかならないものだろうかと、人々は思う訳です。
そこで考えたのが、高野山は奥之院に墓を建てるというものです。少しでも説法の行われる奥之院の近くに墓を建てていれば聞き逃さすことはないだろうという目論みです。一の橋から奥之院御廟橋の間に沢山の墓があるのは、そういう理由からなのです。
当時の弥勒信仰への熱意を感じたくて、奥之院参道にある戦国武将の墓を見てきました。彼らは、ブルーシートを広げて花見の場所取りをするがごとく、いまも弥勒如来の説法を聞くための場所取りをしているのです。
戦国武将の墓
奥之院参道、一の橋から御廟橋までの有名な戦国武将のお墓を、順に見ていきたいと思います。何故、戦国武将かというと、有名な人物のお墓には名前の書かれた看板が立てられているからです。お墓に埋もれたお墓は、看板という目印がなければ誰の墓なのか分からないです。ちなみに、戦国武将のお墓はその武将が建てたのではなく、家臣や子孫、その武将を信奉する人々が建てたもののようです。
武田信玄の墓

武田信玄と息子勝頼の墓。この日は良い感じに霧が出ていてとても神秘的な写真が撮れました。ただ、写真を観てもらって終わりというのも詰まらないので、それぞれの武将の辞世の句を載せておきます。
『大ていは 地に任せて 肌骨好し 紅粉を塗らず 自ら風流』
現代語訳としては「この世は世相に任せるものだ。その中で自分を見出して死んで行く。見せ掛けで生きてはならない。生きるのは、本音で生きることが一番楽である」ということらしいです。死に様にも風流を見出す、美意識を感じます。
上杉謙信の墓(廟)

武田信玄のお墓のすぐ近くにあるのが、上杉謙信の霊廟。質素な武田信玄のお墓に比べて、上杉謙信の墓は豪華です。何しろ墓じゃなくて廟ですからね。墓とは石でできた塚状のもので、廟とは建物になります。
『極楽も 地獄も先は 有明の 月の心に 懸かる雲なし』
というのが、上杉謙信の辞世の句と言われているものです。現代語訳としては「私の死後、私は極楽、地獄に行くのかはわからないが、どちらに行くことになっても今の私の心境は、雲のかかっていない明月のように一片の曇りもなく、晴れやかである」ということらしいです。
伊達政宗の墓

独眼流で有名な伊達政宗のお墓です。立派な五輪塔の手前に石造りの鳥居がありました。伊達政宗、伊達家が神道の信者だったからかも知れないです。辞世の句には
『曇りなき 心の月を先立てて 浮世の闇を照らしてぞ行く』
があります。現代語訳としては、「心の清らかさや真実が、困難な状況を乗り越える助けになる」という意味ということだそうです。
井伊直政の墓(廟)

井伊直政の霊廟です。井伊直政は、桜田門外ノ変や安政の大獄で有名な井伊直弼の先祖になります。徳川家康の懐刀、徳川四天王、徳川三傑に数えられ英傑です。超美男子だったらしいですよ。
『祈るぞよ 子の子のすへの 末までも まもれあふみの 国津神々』というのが、井伊直政の辞世の句です。
「祈ります。近江の神様、子孫の末まで守って下さい」というものです。そう聞くと、井伊直弼の最期は無念だったと思います。
薩摩島津家の墓

薩摩島津家の墓です。初代藩主・島津家久、二代藩主・島津光久、光久の長男の島津綱久が祀られています。ここに出てくる人々の辞世の句を探したのですが見つかりませんでした。代わりに家久の兄弟てある島津歳久の辞世の句を載せておきます。
『晴蓑めが玉のありかを人問はば、いざ白雲の上と答へよ』
「歳久の魂は、どこにいったのだと人に問われたら、白い雲の彼方(浄土)に消え去ったと答えてください」という意味だそうです。
島津歳久は豊臣秀吉から疑惑を掛けられ、兄からも追われ、島津家への責めを一身に背負う形で自害しました。この辞世の句は、歳久が自決する直前に書かれました。そう知ってから読むと、なんと潔く、清らかな句だろうと心を打たれます。
石田三成の墓

ご存じ石田三成のお墓です。豊臣政権の奉行であり、豊田秀吉の死後、徳川家康打倒のため西軍を組織し、関ヶ原の戦いで敗れ京都の鴨川の六条河原で処刑されました。
『筑摩江や 芦間に灯す かがり火と ともに消えゆく 我が身なりけり』
「琵琶湖の葦原に灯されているかがり火が消えていくように、自分の命ももうすぐ消えていくのだな」という意味です。死を受け入れた諦めと覚悟の感じられる句です。
明智光秀の墓

謀反によって、主君・織田信長を本能寺の変で焼き討ちにした明智光秀の墓です。パッと観て、みすぼらしい小さなお墓です。謀反人として扱われてきたので仕方ないかとも思いますが、最近では非常に頭が良く、人柄にも優れた人物であったとの評価もあります。
辞世の句には『心しらぬ 人は何とも言わば言え 身をも惜しまじ 名をも惜しまじ』とありますが、これは後世の創作で、光秀は辞世の句を残していないそうです。
豊臣秀吉の墓

豊臣秀吉の墓です。写真では一部しか写っていませんが、かなりの規模があります。秀吉の墓と書きましたが、豊臣家の墓所で、母公・大政所、大納言秀長、夫人の「ねね」の墓が鎮座しています。
当時、豊臣秀吉は織田信長に続き、紀州攻めを行い、高野山にも攻め込もうとしました。しかし、木食応其上人の説得によりそれを中止。その後、応基上人に帰依して高野山の復興に勤めました。秀吉が計画を変えてくれていなければ、今の高野山はなく、焼き討ちにされた根来寺のような状態になっていたと思われます。そういう訳で、この墓所は県指定の史跡として大切にされています。
他にも、豊臣秀吉ゆかりのものとしては、秀吉が高野山で母の法要を執り行ったときに愛でたと言われる、清浄心院の傘桜、別名・太閤桜などもあります。
『露と落ち 露と消えにし我が身かな 浪速のことは 夢のまた夢』
有名ですが、秀吉の辞世の句です。底辺から天辺まで駆け抜けた男だからこそ、それを夢と言えるのだと感じました。
織田信長の墓

御廟橋のすぐ近くにある織田信長の墓です。知名度からすれば小さなお墓ですが、場所は奥之院からほど近い良い場所にあります。
『人間五十年 天下のうちをくらぶれば 夢幻の如くなり、一度生を得て 滅せぬものの あるべきか、これを菩提の種と思ひ定めざらんは、口惜しかりき次第ぞ』
「人の一生とは、50年程度のものだ。天下のここと比べれば、夢や幻のようなものである。一度生を受けたのであれば、いつかは滅びるものだ」という意味です。
ザ・辞世の句と言っても過言ではない、織田信長の辞世の句です。常に人生の儚さを想い、死を傍に置いてきたからこそ、あんなに激しく生きれたんだなって思います。日本版メメント・モリだなって感じました。どうせ死ぬなら、全力で生きてやる! そんな心意気が見て取れるような気がします。
※
ここまで戦国武将のお墓と辞世の句を見てきました。辞世の句を載せてしまったのは、当時の弥勒信仰を知る上では完全に余計だったと反省しております。しかし、その人の生き方を知るのには、死に様を知るのが手っ取り早いのではないかと思うのです。
それはさておき、霧に霞む世界で、実際に殺し合いをした人達のお墓が肩を並べているのを見ると、この現世での立場を超えた浄土への、強い願いを感じずにはいられません。霧に濡れ、苔むした墓石の下に、56億7000万年後のその時を願う信仰だけが、今も一途にリアルなのでした。

嘘は本当の話
高野山を観光をする上で、予備知識なしで弥勒信仰を感じることは、滅多にないのではないかと思います。奥之院の参道に、何故こんなにも沢山のお墓が建てられているのかということも、事情を知らなければそのまま通り過ぎてしまうことでしょう。
これも事情を知らなければ、弥勒信仰に関連付けることもないかも知れませんが、御廟橋を渡った左手にある祠に弥勒石という石が納められています。長細い俵形をした石で、祠の格子の隙間から片手を差し入れ、持ち上がれば願いが叶うというものです。確か、善人には持ち上がり、悪人には持ち上がらないという話もあったかと思います。
弥勒石という名前だけあって、弥勒信仰に関係するものであるのは推測されますが、この石はなんと弥勒菩薩がいらっしゃる兜率天から落ちてきたというのです。大きさの割に結構な重さがあり、長年多くの人に触られてきた表面には金属質の光沢があります。空から落ちてきたことを考えれば、これって隕石じゃないの?と思うのですが真偽の程は不明です。昔の人達は、きっとその石を通じて、少しでも弥勒菩薩の存在を感じようとしていたのかも知れません。
※
ちなみに、高野山には『みろく石』というお菓子もあります。一の橋から金剛峯寺の方に少し歩いた所にある、『みろく石本舗 かさ國』という和菓子のお店で売っている高野山名物です。前述した弥勒石を模ったお菓子で、スッキリした甘さの餡子が魅力です。ちなみに、かさ國は金剛峯寺御用達の和菓子屋で、どのお菓子を食べても美味しいです。下に挙げる写真は、弥勒石を愛でた後、銘菓みろく石を頂き、みろく石本舗かさ國で店内の様子を撮影した写真です。

56億7000万年ほど早いですが、弥勒菩薩が高野山に降臨しました!
という風に見える写真ですが、本当は嘘です。この写真は、ショーケースの中に飾られていた広隆寺の弥勒菩薩半跏思惟像のミニチュアを撮ろうとしたものです。しかしながら、店内の風景に弥勒菩薩半跏思惟像のシルエットがぼんやり浮かび上がっているように見えるのではないかと思います。実際は逆で、弥勒菩薩を撮ろうとしたら、ショーケースのガラスに映り込んだ背後の風景にピントが合ってしまった写真なんです。
つまり、現実のように見える店内の風景がガラスに映り込んだ幻で、幻に見える弥勒菩薩の姿の方が目の前にある現実なのです。色即是空、空即是色。確かに、現実とは「夢幻の如くなり」です。現実が幻で、幻が現実なのだとすれば、僕の話も本当が嘘で嘘が本当かも知れませんね。


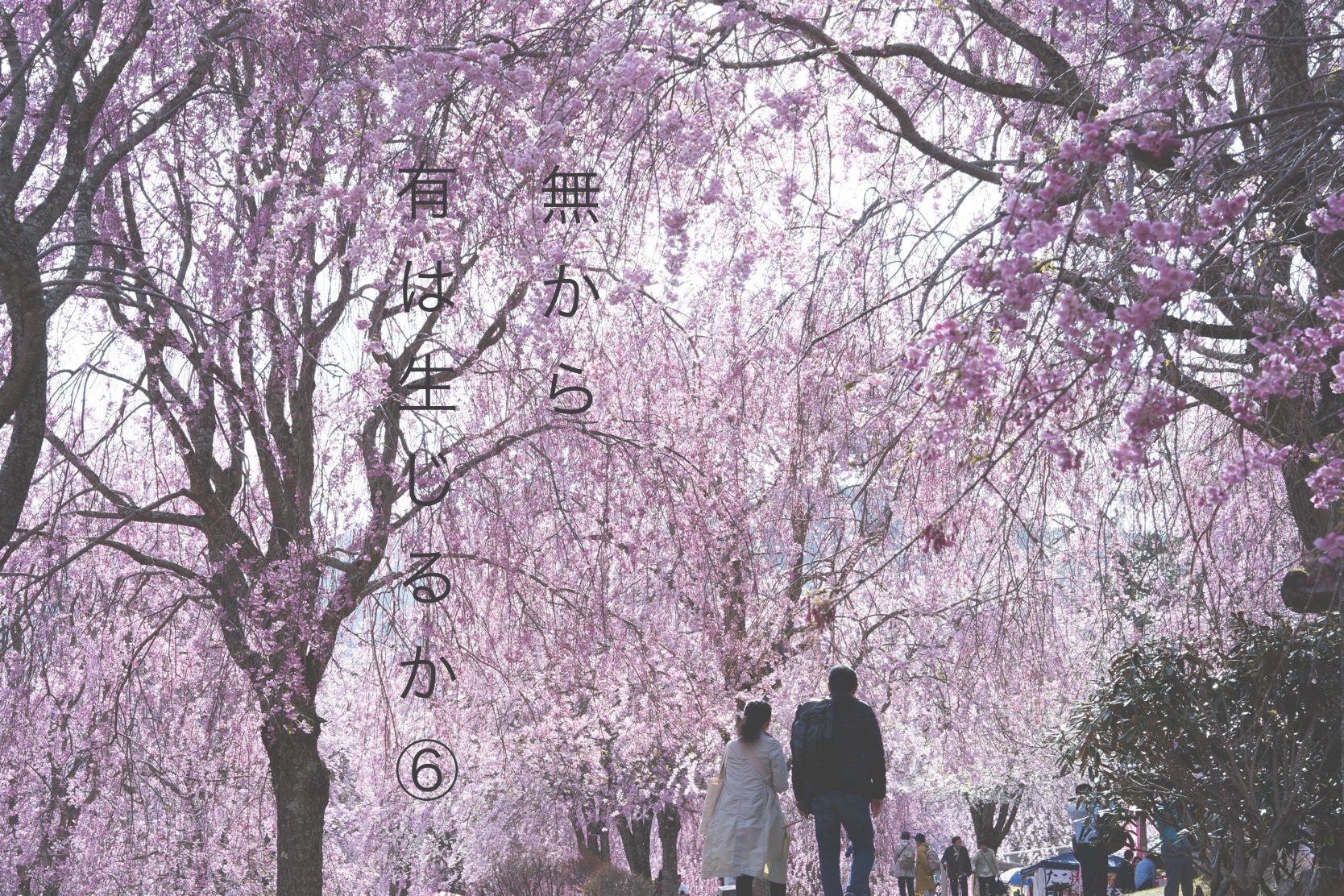
コメント