この記事は、『無から有は生じるか④ -相対の崩壊、そして-』という記事からの続きになります。先ずは、そちらの方からお読み下さい。
仏教に見る始まりの二つのもの
さて、ここまで話を進めてきて、結局は神話の語る内容を超えてはいないのではないかと感じています。ただ、ほんの少しだけ、表現の仕方を変えているだけに過ぎないのかも知れません。おそらくは、僕のしている話も、特定の時代と地域の在り来たりな神話なのでしょう。

『無から有は生じるか① -創世神話-』の中で、仏教は創世神話を持たないと書きました。そして、仏教に関しては後でもう一度書くとも書いています。これまでも仏教に関しては、多くの部分、特に悟りに関しての部分で話していますが、これから書く内容が、『後で書く』と言った内容になります。
ここまで、創世神話の無からの創造と、創世に関わる相対する二つの存在に付いて考えてきました。それらは、ヒンドゥー教や仏教の悟り、道家の道(タオ)の思想に繋がります。始まりを記した創世神話は、それぞれの宗教、思想の根源に繋がっていくのです。おそらく、世界の始まりこそが、それらの物語の真髄であるからなのかも知れません。
それでは、仏教はその始まりに類似の構造を持っているのでしょうか。仏教の開祖であるお釈迦さまは、悟りを開いたとき、あるビジョンを見ています。それが縁起です。『物事には必ず原因と結果があり、それ自体では存在しないという考え方』のことです。お釈迦さまは、これを知識として知ったのではなく、ビジョンとして見たのです。つまり、これこそが仏教の真髄と言えるのではないかと思います。
そして、このビジョンには、確かに二つのものが存在します。無論、それは原因と結果です。しかし、この原因と結果は対立関係を示してはいません。そこには時間関係があるだけです。原因があって、そこから因縁が発展して結果があるのです。だからこそ、結果としての苦しみを生み出す因果を遡って、苦しみの原因を探り当て、それを滅することにより苦しみを解消する、縁起の法が成り立つのです。
しかし、全仏教徒の反感を買いそうではありますが、僕はこの理論はある意味間違っているのではないかと思うのです。ただ、実のところ、この考えは、僕の意見というのではありません。科学者であり、仏教、特に唯識研究者でもある泉美治氏が、NHKラジオ『こころの時代』の中で仰っていたことです。
因果は時間関係ではない
泉氏は、「原因があって結果があるというのは大きな間違いだ。原因と結果は時間的関係ではなく、論理的関係である。縁というのは、要因を原因に転化すると同時に結果を生む」と仰っています。かなり分かりにくいですが、具体的な例を挙げてくれていました。
親子関係に関して、原因と結果を時間関係に則して考えるなら、親が存在するから子が存在するのです。原因としての親が先に存在し、時間の経過によって、結果としての子が後で存在することになります。説明するまでもなく、時間的関係に基づいて考えれば、それ以外の答えはありません。しかし、泉氏はこの考え方を、西洋的思考の弊害だと言います。
つまり、親は子ができた瞬間に、親になったのです。逆に言えば子は、親になった瞬間に子になったとも言い換えることができます。瞬間と言いましたが、この考え方には時間の流れは存在しません。完全な同時です。要因としての親子関係を転化した瞬間、原因としての親と、結果としての子が同時に発生するのです。

親と子という関係に限って言えば、それらは相対し対になっています。ただ、そもそも、時間関係を排除できるなら、原因と結果もまた相対し対になるものなのです。唯識における主体と客体の関係も、この関係を違う表現で表しているだけだと思います。
双子の量子のイメージ
この関係をイメージしやすくするには、量子もつれ状態の双子の量子の考え方を当てはめれば、感覚的に理解しやすくなると思います。一つのイベントで発生した二つの量子は、どれだけ離れていようとも一方の状態を測定するともう一方の状態が瞬時に確定するのです。それは何億光年離れていようがです。
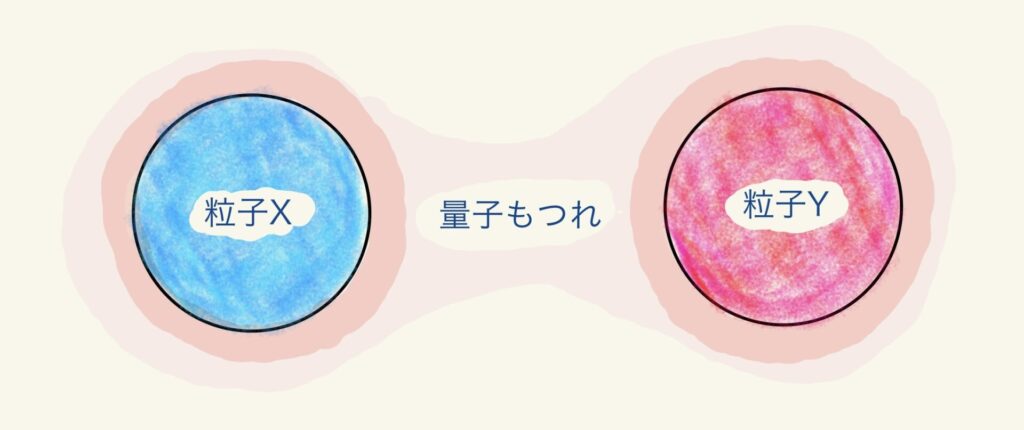
つまり、縁起における原因と結果は、相反するもの、もしくは対になる二つのものとして成り立ち得ると思うのです。やはりお釈迦さまが見たビジョンである縁起にも、他の理論や教義にある相反する二つのもの、ないしは対になる二つのものが間違いなく含まれているのです。
ちなみに、因果を辿って苦しみを生み出す原因を滅することにより、苦しみを解消する縁起の法が間違っているのではないかと書いたとき、僕は『ある意味』と断りを入れています。つまり、すべてを否定している訳ではないのです。僕が否定したのは、縁起の法を時間的関係に限定しているところであって、縁起の法に関する解釈を拡大していけば、否定は限定されたものに過ぎないのです。
時間的関係を排除してもなお、縁起の法は成立すると考えています。泉美治氏が言ったように、時間的関係は論理関係に置き換わったのでのであり、だからこそ、それらは対の関係であり、双子の量子がそうであるように、片方に加えられた変化は瞬時に、もう片方を変化させます。つまり、時間的関係が無くても、原因に与えられた変化は結果を動かし、結果に加えられた変化は、原因を変化させることができるのです。
それはマスターキーとして
ここまで、『無から有は生じるか?』という問いに対して答えを探してきました。途中というか、大半はその疑問から発展した内容になってしまいました。そうでもしなければ答えられないほど、その問いは根源的な問いなのだと思います。
仏教において、存在の有り様を語る言葉があります。『色即是空』という言葉です。般若心経に出てくる言葉として有名で、形あるものは、すべて因縁によって成り立っているのであり、本質的な永遠不滅の実体はないという意味で使われます。それを知ることによって、苦しみの原因である執着から解放されようとするのです。
しかし、この考えも十分ではないと僕は考えます。色即是空という言葉は般若心経だけでなく、他のお経の中にも見出すことができるのです。維摩経の中にも登場し、『不二法門』という思想へと発展していきます。相反する概念は別々のものではなく、一つのものの部分であると説く教えです。善と悪、生と死、我と無我など二項対立は別々のものではなく一つものと考えるのです。この思想は、真言宗などに見る金胎不二の思想や、ヒンドゥー教の不二一元論と同じだと言えるだろうと思います。つまり、それらの相反するものは別々ではなく、一つであると伝える教えとして色即是空を挙げているのです。色と空は二項対立する別々のものではなく、それぞれがそれぞれを肯定するもの、つまり対をなす一つの存在なのです。
ここでも二つのものの相反する関係は否定され、色即是空の教えですらが対になる一つのものを伝えているとみなされています。これもまた、無から有は生じるかという問いに対する、穴を掘って小山を作るというホーキング博士の答えと同じ論理構造です。維摩経においては、『色』が小山であり、『空』が穴として、対の関係を築いているのです。

無から有は生じるかという問いに対する答えは、幸福とは何か?とか、悟りとは何か?とか、時間とは何か?とか、永遠とは何か?などといった、あらゆる問いに対する答えとなり得る、マスターキーのような答えになるのではないかと考えています。
何故なら万物は無から生じているからです。時間、空間、物質、あらゆる有は原初の相対が姿を変えながら展開する花びらのようです。そして、花占いでもするように花びらをめくっていけば、最後には何も残らない『それ』を見付けることになるのです。つまり、僕は無から有は生じると考えています。だからこそ、それはマスターキーとして、すべての扉を開くのです。
有生於無
この記事を書く上で調べものをしながら、出会ったメッセージがあります。それは遠い過去に記された言葉です。偉そうなことを書きながらそんなことも知らなかったのかと笑われそうでお恥ずかしいのですが、道家の始祖である老子が伝えたとされる言葉です。最後に、その言葉を添えておきます。
天下萬物生於有、有生於無。
『この世の万物は有から生じ、有は無から生じる』という意味です。つまりは、そういうことなのだと思います。

※
追伸、電子書籍を販売しています。読んでいただけると嬉しいです。→ こちらをクリック、お願いします。
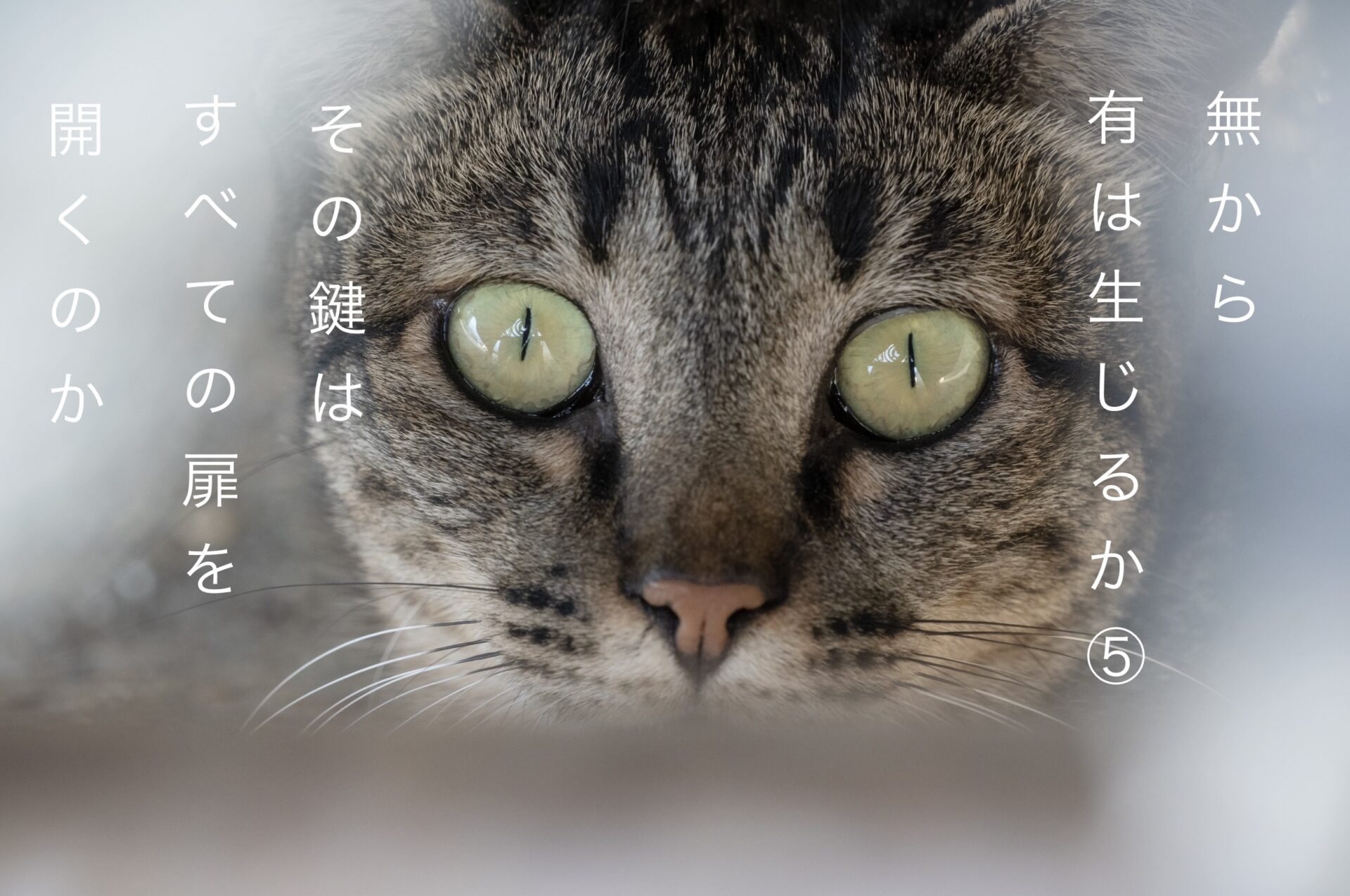


コメント