『シビル・ウォー:アメリカ最後の日』を観てきました。今回も、ほぼネタバレですので、映画鑑賞後にお読みください。
現実を描き出すifの世界
内容は、アメリカ合衆国の内戦という状況を、ジャーナリストの視点から描いた作品です。作品タイトルから、正義と悪に分かれた激しい戦闘が行われ、最終的に負けるかと思われた正義側が、ギリギリのところで逆転し正義が勝ってアメリカ万歳!といった内容かと思われると思いますが、まったくもって違います。この辺が、観客の期待を裏切るところです。映画において、観客の期待を裏切るということは、最高の賛辞でもある訳ですが、この映画においては上手く機能していません。主人公達は戦場には居合わせますが、戦闘には参加しません。
映画自体も、傍観者としてのジャーナリストの視点から描かれています。つまり戦争映画ではないのです。それを期待して観にくる観客と、この映画を楽しめる観客とでは客層自体が違っていると思います。多くの観客が期待を裏切られ、明確な爽快感も得れず、何かが足りないモヤモヤした気持ちを引き摺って映画館を後にすることだろうと思います。僕の個人的印象としては、ロードムービーとドキュメンタリーの手法を使った社会派映画、ないしはヒューマンドラマといったものでした。そして、そういう視点で観てみれば、この映画は大変素晴らしい映画だと言わざるを得ないのです。
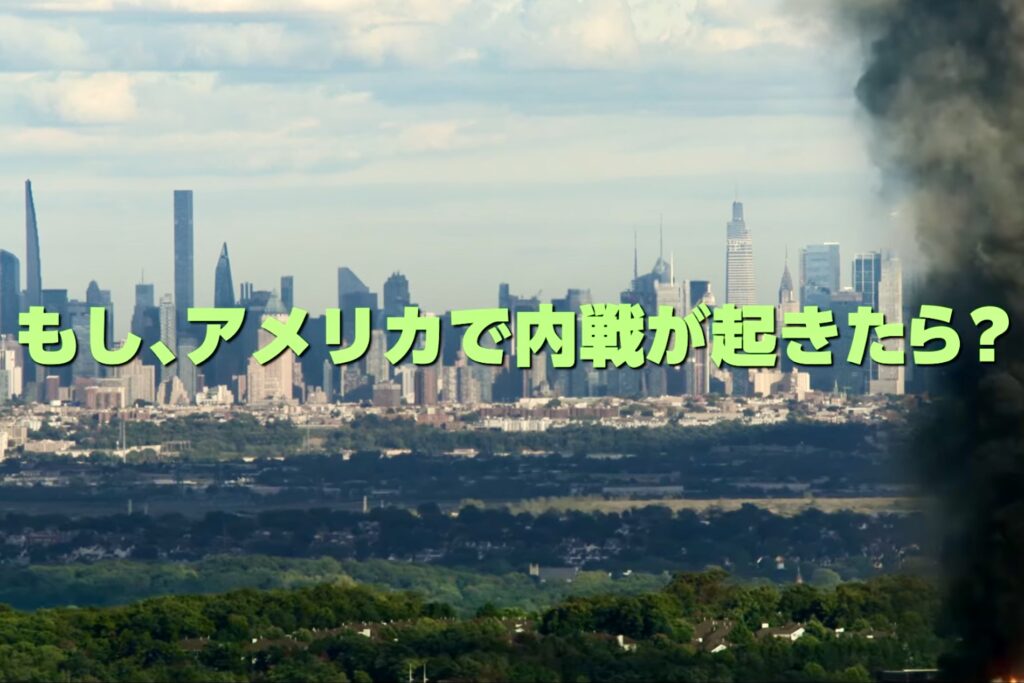
では、どこが素晴らしいのかというと、やはり一番は、現代におけるアメリカの内戦という舞台設定にあると感じます。現実の世界にifの世界を重ね合わせることにより、現実では隠されている、アメリカとは何なのか、人間とは何なのかを暴き出すことに成功していると思うのです。ただ、この辺も映画や音楽などで良きアメリカに親しんで、少なくともアメリカ文化を愛したことのない日本人には実感し難いところです。とても素晴らしい映画だけど、日本人においては観る者を選ぶ映画だなっていうのが率直な印象です。
分断の種子:What kind of American are you?
映画は、アメリカ連邦政府から、テキサスとカリフォルニアを中心とする19州が離脱し、内線状態にあるというところから始まります。そこに至る経緯は直接的には描かれていません。登場人物の交わす会話の中の「3期目の任期中に後悔したことは?」「FBIを解散させたのは懸命な判断でしたか?」「米国民への空爆をどのように考えていますか?」という台詞から、アメリカ大統領がファシスト的な独裁者となったことが推測される程度です。ただ、大統領が独裁者となり、国民を空爆によって殺害したのなら、怒ったテキサスとカリフォルニアが戦闘を仕掛けるのも納得がいきます。
それでも、日本人には感覚的に実感が得にくいところは残るかも知れません。しかし、州というものの歴史的成り立ちとそれを原因とした独立性を知れば、実感として理解できるかと思います。テキサスもカリフォルニアも元々はメキシコの一部であり、独立国だった時期もあるのです。つまり、アメリカは合衆国制度の根本に分離独立の種子のようなものを、成り立ちから抱えて続けているのだと思います。その危うさがなかなか日本人には実感し難いところです。
ちなみに、アメリカの合衆国が何故合州国ではないのかという疑問を感じた方もいらっしゃると思います。英語では、United States of Americaなのですから、合州国が正解のはずです。これは幕末時代の江戸幕府の役人が中国の古典から引用したのだそうです。何故中国? それも古典と思うのですが、民衆が集まって作ってる国、つまり民主主義国家という程度の意味のようです。紛らわしくて困ったものです。

話を戻すと、現実にはアメリカは今のところ分離せずに存続し続けています。その分離への力を抑え付け、一つの国家に纏め上げているのが『アメリカとは何なのか?』という問いに対する答えです。その答えが存在するからこそ、アメリカはアメリカ合衆国として存続し続けているのです。その問いは、この映画の中で、映像として繰り返し問い掛けられ、その度に否定されます。多くのアメリカ人が愛した良きアメリカは、この映画の中でことごとく破壊されてしまっていました。古き良きアメリカが残っているように見える田舎町でも現実から逃避し体裁を整えているに過ぎません。中盤のクライマックスのシーンで象徴的な台詞が現れます。「What kind of American are you?」という台詞です。「お前は、どの種類のアメリカ人だ?」という意味ですが、アメリカ人であるための一つの共有されていた理想は失われ、既に種類と条件が必要とされている、つまり分断は起こってしまっているのです。
リーとジェシーに起こる変容
ニューヨークから始まった主人公達の旅は、キッチュな人々との出会いを繰り返しながら、そして危機的状況に遭遇しながら目的地であるワシントンD.C.へと向かっていきます。主人公達の旅と書きましたが、この映画は群像劇的要素が強く、トムクルーズの映画ほど主人公が強調されることはありません。最初の頃はベテラン戦場カメラマンのリー・スミス(キルステン・ダンスト)が主人公かと思っていました。ただ、ストーリーが進んでいく内に、ドラマ自体が駆け出しの新人カメラマンのジェシー・カレン(ケイリー・スピーニー)の成長を描いていることに気付かされます。

長年悲惨な戦場を駆け回ってきたリーは、映画の序盤から既に精神的に追い詰められていました。中盤のクライマックスの後、古い友人のサミー(スティーヴン・マッキンリー・ヘンダーソン)を亡くし、リーの精神は更に追い詰められていきます。この映画の最大のクライマックスであるホワイトハウス突入のシーンではPTSDを発症したように身動きが取れなくなります。ドライバーのジュエル(ワグネル・モウラ)に助けられながら何とか先に進めるレベルです。ただ、個人的には、サミーの死によって、ジャーナリストとして非情に徹してきたリーが、人間性を取り戻した瞬間だったのではないかと感じています。その後、リーが被写体にレンズを向けシャッターを切ることはありませんでした。彼女は身動きのできなくなっている間に、カメラマンから人間への変容を遂げたのだと思っています。

ちなみにこのホワイトハウス突入から大統領殺害に至るシーンの没入感はもの凄いものがあります。まるで自分が戦闘の一部になっているような感じがします。この映画は戦争映画ではないと書きましたが、他の戦争映画でもこれ程迫力のあるシーンはなかなか観たことがありません。このシーンだけでも、この映画を観る価値はあります。
それぞれの選択
WF(西武勢力)の兵士と一緒にホワイトハウスへ突入した主人公達は、その奥に隠れている大統領を探し追い詰めていきます。ここまで話が進むと、物語は単なるロードムービーから、『竜退治のテーマ』ないしは『宝探しのテーマ』へと変貌を始めます。主人公が苦難の末に、竜の住む洞窟を訪れると竜を倒し、竜が隠し持っていた宝物を手に入れ大人へと成長するというお伽話の典型です。そう考えてから想い返してみると、高いバリケードで囲まれたホワイトハウスは確かに悪い竜の潜む洞窟のようでもありました。
大統領を追い詰めたと思った瞬間、功を焦ったジェシーは大統領の護衛の前に飛び出してしまいます。確実に撃たれてしまう状況のジェシーを守るため、リーが盾となって代わりに撃たれてしまうのです。その時のリーはカメラマンであるより、人間だったのでしょう。それなのに、ジェシーは自分のために命を投げ出してくれたリーに視線を向けることもなく、大統領の元に進んで行きす。このシーンは人間とは何か、ジャーナリズムとは何かという問いに答えてくれるとても重要なシーンです。

そして、このシーンは映画の序盤のガソリンスタンドのシーンと明らかに対をなしています。給油のために訪れたガソリンスタンドで、リーとジェシーはロープで吊るされ拷問にあう略奪者を目撃します。余りにも凄惨な状況にシャッターを切れなかったことを悔やむジェシーに、リーは「振り返らず、何も言わず、ただシャッターを切れば良い」というようなことを言ったと思います(すいません。正確には覚えていません)。その時のリーのアドバイス通りに、ジェシーは行動したのです。と言うよりも、リーと同じプロのカメラマンに成長したからこそ、ジェシーはその行動を取ることができたのです。ジェシーは、薄情な訳ではなく、プロのカメラマンつまりジャーナリストとして、個人の感傷を断ち切り、より大きなもののために働いているのです。
何故、モノクロのフィルムカメラなのか?
ついに兵士達が大統領を捕獲し射殺します。大統領に最後の言葉を聞いた後、ジェシーは大統領殺害の決定的な瞬間という、カメラマンにとって最高のスクープ写真を手に入れることになります。これが、竜退治のテーマにおげる秘められた宝物です。そして、映画はエンディングを迎えます。
ただ、本当にこの映画はそれで終わりなのでしょうか。アメリカ人とは何なのかという問いに、映画はまだ答えられていないような気がします。ここからは僕の勝手な妄想ですが、その答えはエンディングにあるのではないのでしょうか。エンディングでは先ず真白な画面が映し出され、ゆっくりと黒いシミのようなものが浮かんできます。少し時間が進むと、それが大統領殺害の場面の写真であることが分かります。つまり、ジェシーが撮ったスクープの写真です。現像液の中に浮かんだ印画紙に、ジェシーの写真が少しづつ浮かび上がってくる様子をスクリーンは映し出しているのです。

映画を観ている間、ずっとジェシーが何故古いフィルムカメラで、おまけにモノクロフィルムで撮影するのかが気になっていました。スタジアムで、持ち運びようの現像キットを使って、フィルムを現像しスマホでスキャンしていました。ジェシーのキャラクター作りの小道具かとも思いましたが、やはり余りに無理があると思ったのです。何十本ものフィルム、それを現像するための道具と現像液の液の重さ、そして、現像やフィルム交換に取られる時間と手間。デジタルカメラが主流の時代、それも戦場という合理性が求められる状況で余りにも非合理です。事実、映画の中でジェシーがフィルム交換をしているシーンは一度も映されていません。あのペースで写真を撮っていたら、30分でフィルム一本は使い切ってしまうはずです。映像にすると有り得ないことが観客にもバレるから、フィルム交換のシーンは入れなかったのだろうと思います。
アメリカ人とは何なのか?
それでは何故そんな無理な設定を導入したのか。僕はこの印画紙に画像が現れるシーンのために、多少の無理は押してもフィルムカメラを使わせたかったのだと思います。フイルム、それもモノクロの現像でなければ、このような手法で画像を浮かび上がらせることはできません。デジタルならバソコンに表示されるだけですし、カラーフィルムなら大規模な機械を使って現像することになります。
もう一度、僕の個人的な意見であることを断っておきますが、この印画紙に浮かび上がる写真こそ、アメリカ人とは何か? ひいては人間とは何か?という問いに対する答えになっているのだと思うのです。
印画紙に浮かび上がった写真は、殺害した大統領を囲んで、高々と銃を掲げ、喜びの笑顔を浮かべる兵士達の姿でした。その様子は、狩りで仕留めた獲物を前に記念写真を撮るハンター達のようにも見えます。それがアメリカ人の本性なのではないかと思うのです。そして、主人公のジェシーもまたアメリカ人です。写真を撮ることを、英語で『shoot』ととも言います。特にスナップ写真などではよく使われる表現で『撃つ』という意味です。写真を撮る人なら分かると思うのですが、写真を撮るという行為は被写体という獲物を見付け、シャッターチャンスというタイミングを計り迷わずにシャッターという引金を引く作業で、被写体に対する狩りと同じ行為です。
そこに現れるのは、獲物に対してどこまでも貪欲で、無邪気なまでの残酷さという本能的衝動です。脚本・監督を手掛けるアレックス・ガーランドは、その衝動をしてアメリカ人であると言いたいのではないかと思うのです。廃遊園地のような場所で、兵士が狙撃兵に襲撃されているシーンがあります。銃を撃つ兵士にどちら側の勢力かを尋ねたところ、「誰かが殺そうとするから、奴らを殺すだけだ」と答えました。そこに善や悪といったヒューマニズムを納得させるほどの理由はありません。この映画の中で、アメリカ人は本能まで丸裸にされてしまったのではないかと思うのです。
アレックス・ガーランド監督はイギリス出身の人物です。アメリカの社会を外側から見て、あえてシニカルにアメリカ人とアメリカの未来を描いてみせたのだと思うのです。それは痛烈な社会風刺であり、予言的警告です。日本人にはますます実感し辛いところではありますが、アメリカ人にとっての切実なリアルなのだろうと感じました。
※
追伸、電子書籍を販売しています。読んでいただけると嬉しいです。→ こちらをクリック、お願いします。



コメント